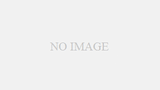子どもに薬を飲ませるのって、本当に大変ですよね。
私にも4歳と1歳の子どもがいますが、上の子は素直に飲んでくれても、下の子は毎回大騒ぎ…。
今回は、小児への薬物投与の基本的な考え方と、飲ませ方の工夫について、薬剤師の立場からわかりやすくお話しします。
目次
① 抗生物質は飲み切る、他の薬は無理に飲ませない
抗生物質や抗ウイルス薬は、症状が良くなっても最後まで飲み切ることが重要です。途中でやめると菌が残って再発したり、耐性菌ができる可能性があります。
一方、咳止めや解熱剤などは、症状が改善すれば無理に飲ませる必要はありません。子どもが眠いときに無理に飲ませようとすると、かえって起きてしまうこともあるため注意が必要です。
② 薬を飲む時間と間隔の考え方
薬には「食後」と書かれていることが多いですが、それは食事のあとが最も飲ませやすいためです。
- 1日3回の薬 → 4時間以上空けていればOK
- 1日2回の薬 → 8時間以上空ければOK
食事とずれても、時間が空いていれば問題ない薬が多いので、気になる場合は薬剤師に相談しましょう。
③ 剤型(粉・水剤・坐薬)の変更で対応
子どもによって「水薬は嫌だけど粉薬ならOK」「粉は無理だけどシロップなら飲める」といった違いがあります。
特に小さな子どもには坐薬も選択肢のひとつ。高熱時に内服できない場合も、坐薬なら対応可能です。医師や薬剤師に相談すれば、剤型変更も可能です。
④ 薬を飲みたくなるような工夫
薬を捨てられたり、吐き出されたりするとイライラしがちですが、怒っても薬は戻りません。
次に飲んでくれるように工夫することが大切です:
- シールを貼るごほうび作戦
- お人形遊びで「アンパンマンも飲んでるよ」
- 薬の時間に歌を歌って気をそらす
⑤ 薬の意味を子どもに伝えよう
子どもでも、きちんと説明すれば理解してくれることがあります。
「しんどいのを治すために飲むんだよ」と伝えるだけでも違います。
それでもダメなら、薬剤師にお願いして、目の前で薬を飲む姿を見てもらうのも効果的です。
まとめ
- 飲ませなくてもいい薬を事前に確認
- 食後にこだわりすぎず、間隔を空ける
- 苦手な薬の形を把握しておく
- 飲みたくなる工夫(シール・人形など)を準備
- 薬の意味を伝えて自発的に飲めるように
次回は、さらに具体的な「薬を飲ませる実践テクニック」をご紹介します!